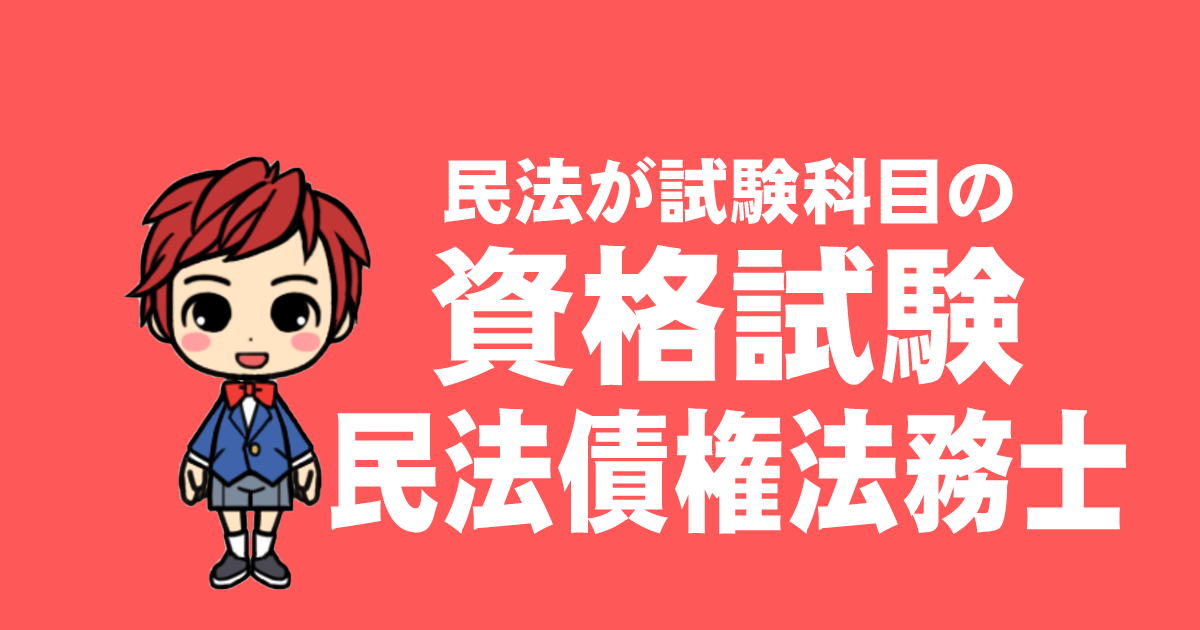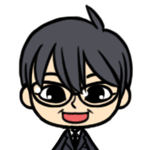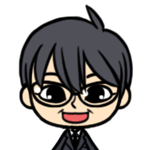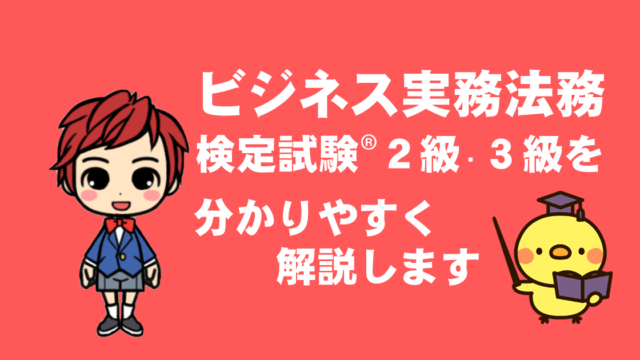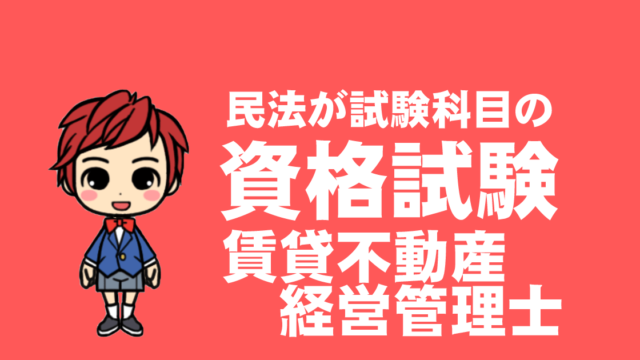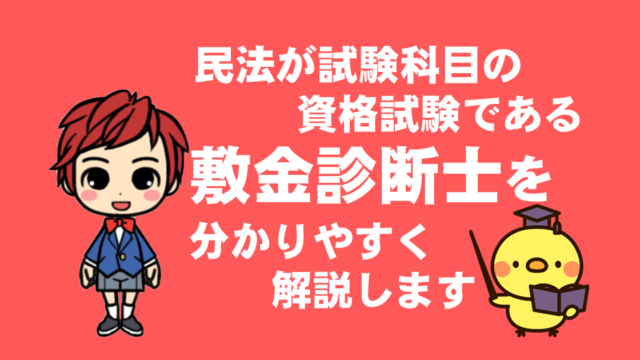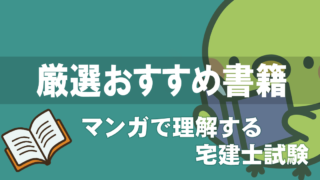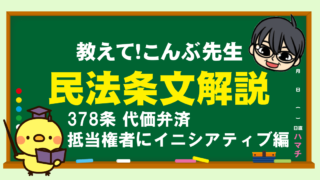民法法務士とは?
民法法務士は、民法に精通し、法務士として社会で活躍する民法のスペシャリストです。
民法は債権法を中心に明治以来の120年ぶりの大改正がされ、2020年に施行されました。改正民法の知識を身に着け、民法法務士認定試験に合格することで、民法のプロフェッショナルとして社会へアピールすることができます。
また、民法の中でも債権法は企業法務や契約実務で最も重要な法律であり、民法法務士認定試験の勉強を通して債権法の知識を深めることで、実務へ大いに役立てることが出来ます。
民法法務士認定試験は、法学部の学生や法律系の資格試験の受験生にも注目されている資格です。法学部の学生は、大学で民法を学びます。大学で学んだ内容を見える化させて、就職活動の際のアピール材料として取得を目指す学生が多いようです。
司法書士試験や行政書士試験の受験生は、試験科目に民法があるため、民法を当然に勉強しています。勉強した内容がそのまま民法法務士認定試験の学習に繋がります。
また、司法書士試験や行政書士試験は難関資格であるため、合格することは容易ではありません。合格できずに試験から撤退する人がいるのも事実です。試験からは撤退したけど、一生懸命勉強した内容を形にするために、民法法務士認定試験の受験を検討する人もいるようです。
民法法務士認定試験に合格するには?民法法務士認定試験について
民法法務士認定試験の合格基準は、正答率70%以上です。
試験日:令和3(2021)年9月19日(日)
試験時間:10:00~12:45(試験時間は2時間30分)
試験会場:東京・名古屋・大阪・福岡
受験料:一般16,500円 学割11,550円(税込)
申込期間:2021年5月18日(火)~8月19日(木)
試験の内容:60問
設問方式:四肢択一、五肢択一、六肢択一。マークシート式試験
出題範囲は、民法第五編全般から出題されます。
ただし、出題頻度の高いテーマが試験のサイトで公表されていますので、まずはこれらのテーマの理解を深めることが得点を稼ぐコツです。
司法書士試験や行政書士試験の勉強においてもこれらは重要テーマです。また、改正民法においても注目の範囲ですので、民法法務士認定試験の勉強を通してこれらの内容を理解することは、実務においても役立つでしょう。
民法法務士認定試験に合格するには?
Before/After 民法改正
『Before/After 民法改正』は、改正の前後で、何がどう変わるのかを232の具体的なケースで紹介しながら解説してくれます。
単に新法を解説するだけでなく、旧法との違いを比較して解説しているので、より改正民法への理解が深まります。
民法法務士認定試験を受ける方へ
民法法務士認定試験は、改正民法が施行され最も注目される資格試験です。民法に精通することで、改正への対策が求められる企業等での活躍の場が広がります。
民法法務士認定試験は、2018年に第1回の試験が実施された民法債権法務士認定試験を前身とする新しい資格です。そのため過去問を中心にした勉強が難しいです。
民法の勉強では、暗記に頼るのではなく、本質を理解することが最も重要です。条文と基本事項・重要判例を押さえた上で、どのような形で問題が出題されても対応できる力をつけることを意識して勉強するようにしてくださいね。
ワカメの「民法が試験科目の資格試験」紹介
第5弾:民法法務士認定試験 ←今ココ!


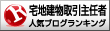
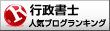

予備試験ブログまとめサイト